
・「できれば」で良いですよ。
・いつでも良いですよ。
・強制ではないです。
上司からの指示で、このように言われるとどう思いますか?

・別にできなくてもいいのね。
・急ぎではないのね。
・やらなくてもいいのね。
きゃ~!優しい~~~!!
「部下想いの、優しい上司」
私は、そう思います。
ですが、このコミュ障上司の部下からすると…

・「できるよね!」ってこと?
・急げってこと?
・やれってこと??
これってパワハラなんじゃない??
え??
なんで?
なぜ、「優しさ」がパワハラになるの??
この記事では、
「優しいパワハラ」に悩む部下:
・上司の言葉の真意が分からず、常にプレッシャーを感じている人。
・「自分が悪いのでは?」と一人で悩んでいる人。
・上司に悪気がないからこそ、強く反発できずにいる人。
無自覚な「優しいパワハラ」をしている上司:
・部下に優しくしているつもりなのに、なぜか信頼関係が築けないと悩んでいる人。
・部下の自主性を尊重しているつもりなのに、仕事がうまく進まないと感じている人。
・自分のコミュニケーションに自信がなく、部下との関わり方を模索している人。
こんなお悩みを感じている方の参考になれば幸いです。
コミュ障上司ってどんな人?
「コミュ障」とは、
本来「コミュニケーション障害」を略した言葉ですが、
ここでは「コミュニケーションが苦手な人」という意味で使います。
「コミュ障上司」の代表的な特徴は、主に2つのタイプに分けられます。
1. 伝え下手で指示が曖昧なタイプ
・指示が漠然としている:
具体的な方法や期限を伝えずに、「よろしく」「適当にやって」など、あいまいな指示を出す。
・言葉足らず:
自分の頭の中では完璧に理解しているため、必要な情報を伝え忘れてしまう。
・報告・連絡・相談が苦手:
部下からの質問や相談に対して、要領を得ない返答をしたり、話をはぐらかしたりする。
2.部下との関わりが苦手なタイプ
・雑談をしない:
業務以外のコミュニケーションを極端に避ける。
・褒める・叱るが苦手:
感情表現が苦手で、部下の頑張りを正当に評価できなかったり、注意すべき点をうまく伝えられなかったりする。
・意見を聞かない:
自分の意見ばかりを主張し、部下の話に耳を傾けない。
私の職場のコミュ障上司の場合
職場のコミュ障上司は、上記の特徴を見事に、全部当てはまっています。
そこに加えて、
・仕事の能力が非常に高く、別部署からも高評価を受けている
・思いやりがあり、優しい
確かに、コミュニケーション不足ではありますが、
仕事においては絶対的信頼があり、問題ないのでは?
さらに思いやりがあって優しいなんて、恵まれているよ。
と思うのですが、
部下からすれば、問題が大ありなのです。

コミュ障上司の弊害
「仕事の能力が高ければ、それでいい」
…どうやら、そうでもないようです。
日々のコミュニケーション不足は、少しずつ積み重なっていき、
部下は次第に、上司を信頼することができなくなります。
あの人は「コミュ障」だから…
なんて言い訳は通らないのです。
連絡事項を一部の人にしか言わない
職場のコミュ障上司は、連絡事項を一部の人にしか言わないのです。
もしかすると、

連絡事項を言うのは、別に全員でなくてもいい。
一部の人に伝えておけば、全員に伝わるだろう。
と思っているのかもしれません。
いずれにせよ、
そのような対応をしてしまうと部下は…
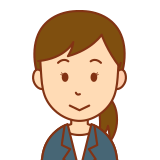
え!?
私は聞いてないよ。
なんで私には教えてくれないの??
私のこと…キライなのかな?
…。
あとは、誰かに頼んでね
職場のコミュ障上司は、指示が雑です。

この仕事の依頼が来たので、うちでやることにしました。
ムリそうだったら、○○さんに手伝ってもらってください。
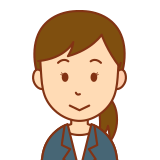
え!?
下っ端の私が、○○さんに頼むの!?
頼みずらいんだけど…。
全部自分でするしかないのかな。
っていうか、そもそも私が担当なの?
職場のコミュ障上司は、極力、部下と関わろうとしません。
なので、部下が困っていることに、気づくことができません。
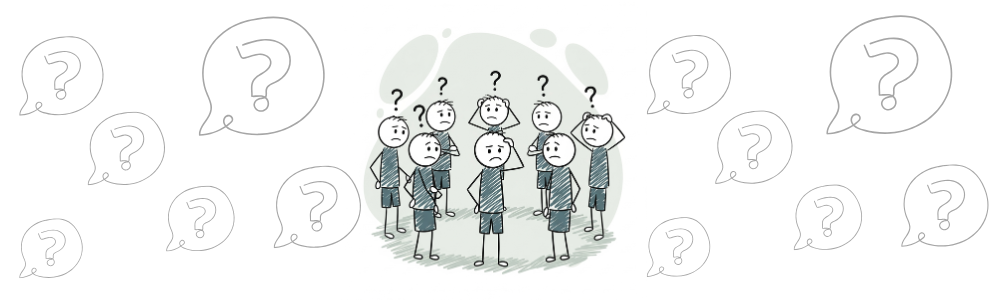
なぜ?優しさがパワハラになるメカニズム
「コミュ障上司の弊害」より、
コミュニケーション不足によって、部下の上司への信頼は高くはありません。
むしろ低く、不満が蓄積された状態です。
こんな状態で、

・「できれば」で良いですよ。
・いつでも良いですよ。
・強制ではないです。
思いやりのある優しい言葉は、
部下の心に響くことはありません。
不満の状態によっては、攻撃的な反応になってしまうのです。
善意の皮をかぶったパワハラ?

・「できれば」で良いですよ。
・いつでも良いですよ。
・強制ではないです。
そもそも、このコミュ障上司の「優しさ」は、本当に優しいのでしょうか?
・部下に嫌われたくない
・衝突を避けたい
という心理が透けて見えませんか?
そして、
「決定権」を部下に移して、責任を回避しているように見えませんか?
だとしたら、善意を言い訳にした巧妙なパワハラ…
と捉える人もいるかもしれません。

解決策(部下編):優しいパワハラから抜け出すための3ステップ
指示が雑で曖昧、連絡漏れなど、
コミュ障上司の弊害によって、
部下は、
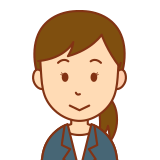
なんでこんなことに
悩まなきゃならないの!!
と、余計なことに時間を使っています。
なので、その悩ましい時間を少しでも減らすため、
部下側でできることを考えてみませんか?
ステップ1:「言葉の翻訳」から始める
上司の言葉をそのまま受け取ると、
『やらなくていいんだ』と誤解してしまい、後で『なんでやってないんだ?』と怒られたり、『どうすればいいか分からず、結局何も手につかない』という状況に陥りがちです。
そうならないために、上司の言葉の裏にある 『本当の意図』 を読み解く練習をしましょう。
コミュ障上司の言葉を、自分の中で「指示」として解釈し直す練習をします。
・「できればでいい」
→自分にできること
・「いつでもいい」
→後回しにしないで、早めに取り組む
・「強制ではない」
→ほぼ強制
・「よろしく」
→この仕事は君に任せる。分からないことがあれば、報告・相談してほしい
・「なんかいい感じでやっておいて」
→具体的な指示は出せないけれど、君の判断に任せる。進捗は適宜共有してほしい
ステップ2:曖昧な指示を「具体的なタスク」に変える
質問することは、決して『仕事ができない』わけではありません。
むしろ、『仕事を確実に進めたい』というプロ意識の表れです。
また、曖昧な指示を具体的にすることで、『タスクの抜け漏れ』 や 『手戻り』 を防ぐことができます。
結果として、上司も部下も安心して仕事を進められるようになります。
「何について、いつまでに、何を、どこまでやれば良いでしょうか?」
と質問し、期限とタスク内容を明確にすることで、不安を解消します。
『いつでもいい』と言われると、つい『じゃあ自分で判断しよう』と思ってしまいがちです。
しかし、その結果、もし上司の意図と違っていた場合、すべての責任を自分で背負うことになってしまいます。
また、最終判断を上司に言わせることによって、決定権を上司にお返しします。
上司に最終的な判断をしてもらうことで、余計なプレッシャーから解放され、上司も自分の役割を再認識することができます。
・期限が曖昧
→では、いつまでに完了すれば一番スムーズですか?
→もし急ぎであれば、今取りかかりますが、優先順位はどのくらいでしょうか?
→だいたい〇〇(例:来週中)までには完了させようと考えていますが、いかがでしょうか?
・指示の内容が曖昧
→具体的にどこまで進めておけばよろしいでしょうか?
→最終的にどのような状態を目指せば良いでしょうか?
・担当者が曖昧
→私の方で進めますか? それとも、他の方と協力して進めますか?
→もし〇〇さんのご協力をいただく場合、どこまでお願いすれば良いでしょうか?
ステップ3:報・連・相の主導権を握る
コミュ障上司は、部下が困っていても、自分から話しかけてくることはほとんどありません。
そのため、『相談したいことがあるのに、なかなかタイミングが掴めない』という状況になりがちです。
いつまで経っても相談の場が持てないと、タスクが滞ったり、不安が募ったりして、余計なストレスを抱え込んでしまいます。
そうならないために、自分からコミュニケーションの場を設定し、仕事を前に進めることが大切なのです。
「相談していいですか?」と聞くのではなく、
「〇〇についてご相談したいのですが、今お時間よろしいでしょうか?」
と具体的な内容を伝えて、上司とのコミュニケーションの場を自ら設定します。
「主導権を握る」うえで役立つ、ちょっとしたコツも加えてみましょう。
短く、簡潔に:
- コミュ障上司は、長い話が苦手なことが多いです。
話す内容を事前に整理し、結論から先に伝えるように意識しましょう。
定期的な機会を作る:
一度話しかけることに成功したら、「今後、〇〇の進捗は週に1度ご報告させていただけますか?」と提案してみるのも有効です。
これにより、今後も定期的にコミュニケーションを取るきっかけを作ることができます。
この「定例化」は、曖昧な指示を具体化するのと同じくらい効果的です。
なぜなら、上司も「この件は、毎週〇曜日に報告が来る」と予測できるようになり、あなたの相談に耳を傾ける準備ができるからです。
また、あなた自身も「いつ相談しよう…」とタイミングを計るストレスから解放されます。

コミュ障上司との共存:上手に付き合うための心構え
被害者意識に陥るのではなく、上司の特性を理解した上で、より建設的な関係を築くためのヒントを提案します。
「優しいパワハラ」に悩む日々から抜け出すためには、まず「心構え」を変えることが重要です。
上司の行動を「嫌がらせ」や「悪意」と捉えるのではなく、「コミュニケーションが苦手な人の行動」として割り切ってみましょう。
この小さな視点の転換が、あなたの心を軽くし、次のステップへと進むエネルギーになります。
1. 期待しすぎない
「上司なんだから、ちゃんとしてくれるはず」
「言わなくても察してくれるはず」
という期待は、残念ながらコミュ障上司には通用しないことが多いです。
上司に完璧なコミュニケーションを期待するのをやめ、
「この上司は、曖昧な指示を出す人だ」
と認識することから始めましょう。
そうすれば、
曖昧な指示を受けたときも「やっぱりな」と冷静に対応できますし、
余計なストレスを抱えずに済みます。
2. 自分は「通訳者」だと考える
上司の言葉をそのまま受け取るのではなく、自分の頭の中で「翻訳」してみましょう。
そして、その翻訳した内容が正しいか、上司に確認する練習をします。
これは、相手の言葉の真意を読み解くトレーニングでもあり、同時にあなたの仕事の正確性を高めることにもつながります。
3. 「報・連・相」を「仕事の進捗管理」と捉える
「報・連・相」は、上司に気に入られるためのものではありません。
「自分の仕事が確実に、かつスムーズに進んでいることを確認するための「自己管理ツール」だと考えましょう。
上司とのコミュニケーションの機会を自ら設定し、そこで曖昧だった指示を具体化する。
これは、あなたの仕事の効率を上げ、余計な手戻りを防ぐための投資なのです。
コミュ障上司との関係は、まるで「言葉の違う人と話す」ようなものです。
被害者として悩み続けるのではなく、あなたが「通訳者」となり、「ファシリテーター(進行役)」となることで、状況をコントロールできるようになります。
それは、あなたのコミュニケーション能力を磨き、どんな上司とでも円滑に仕事を進められるスキルへと変わっていくはずです。
解決策(上司編):部下との信頼関係を築くための第一歩
優しいつもりなのに、なぜか部下との間に溝ができてしまう。
そんな悩みを抱える上司の方もいるかもしれません。
もしかしたら、その「優しさ」は、部下の心に届いていないのかもしれません。
部下との関係を改善し、チームを円滑に進めるためのポイントを考えてみましょう。
指示を「伝わる言葉」に変える
「できるだけ」や「いつでもいい」といった言葉は、部下に選択肢を与えているようで、実は大きな不安を与えています。
曖昧な表現を避け、具体的なタスクと期限を明確に伝えましょう。
例:
- 悪い例: 「あの資料、できれば早めに適当に作っておいて。」
- 良い例: 「〇〇の資料を作成してほしい。来週の火曜日の会議で使うから、月曜日の午前中までにたたき台を提出してくれるかな。分からないことがあれば、いつでも聞いてね。」
報・連・相の「場」を意識的に設ける
「部下から何かあれば来るだろう」と待っているだけでは、コミュニケーション不足は解消されません。
あなたから積極的に話しかける機会を作りましょう。
例:
「〇〇について話したいんだけど、15分だけ時間をもらえるかな?」と、時間を区切って相談の場を設ける。
「最近、仕事の進み具合はどう?」と、進捗確認を兼ねた声かけをする。
「ちょっと聞きたいんだけど」と、雑談から入ることで、部下の緊張をほぐす。
「小さな成功」を承認する
部下の頑張りを言葉にして伝えることは、信頼関係を築く上で欠かせません。
大げさなことでなくても構いません。
「ありがとう」「助かったよ」といった一言が、部下のモチベーションにつながります。
例:
- 「この前の資料、すごく分かりやすかったよ。ありがとう。」
- 「〇〇さんの対応が丁寧だと、取引先からも褒められたよ。いつも感謝している。」
- 「急な依頼だったのに、快く引き受けてくれて助かったよ。」
これらの行動は、部下からすると「自分のことをちゃんと見てくれている」という安心感につながります。
それは、単なる「優しい上司」ではなく、「信頼できる上司」になるための第一歩です。

まとめ:コミュ障上司との健全な関係を目指して
この記事では、「善意の皮をかぶったパワハラ」のメカニズムと、そこから抜け出すための具体的なステップを見てきました。
しかし、ここで改めて強調したいのは、これは「どちらが悪い」という話ではないということです。
コミュ障上司に悪気はありません。
彼らはただ、コミュニケーションの取り方が不器用なだけで、もしかしたら過去に何らかの経験から、部下との関わり方を模索しているのかもしれません。
一方、部下も「パワハラだ!」と一方的に決めつけるのではなく、自分の心を守りながら建設的に状況を改善する方法を探す必要があります。
重要なのは、**「歩み寄ること」**です。
部下は、
上司のコミュニケーションの特性を理解し、曖昧な指示を具体化するための「通訳者」となることで、自身のストレスを軽減し、仕事をスムーズに進めることができます。
上司は、
自身のコミュニケーションが部下にどう伝わっているかを知り、少しの工夫で信頼関係を築くことができます。
お互いが相手の状況を想像し、ほんの少し歩み寄ることで、職場はより安心できる場所に変わっていきます。
そして、この「優しいパワハラ」を乗り越えた経験は、あなた自身の人間関係をより豊かにする、貴重なスキルになるはずです。

想像力を解放セヨ!!
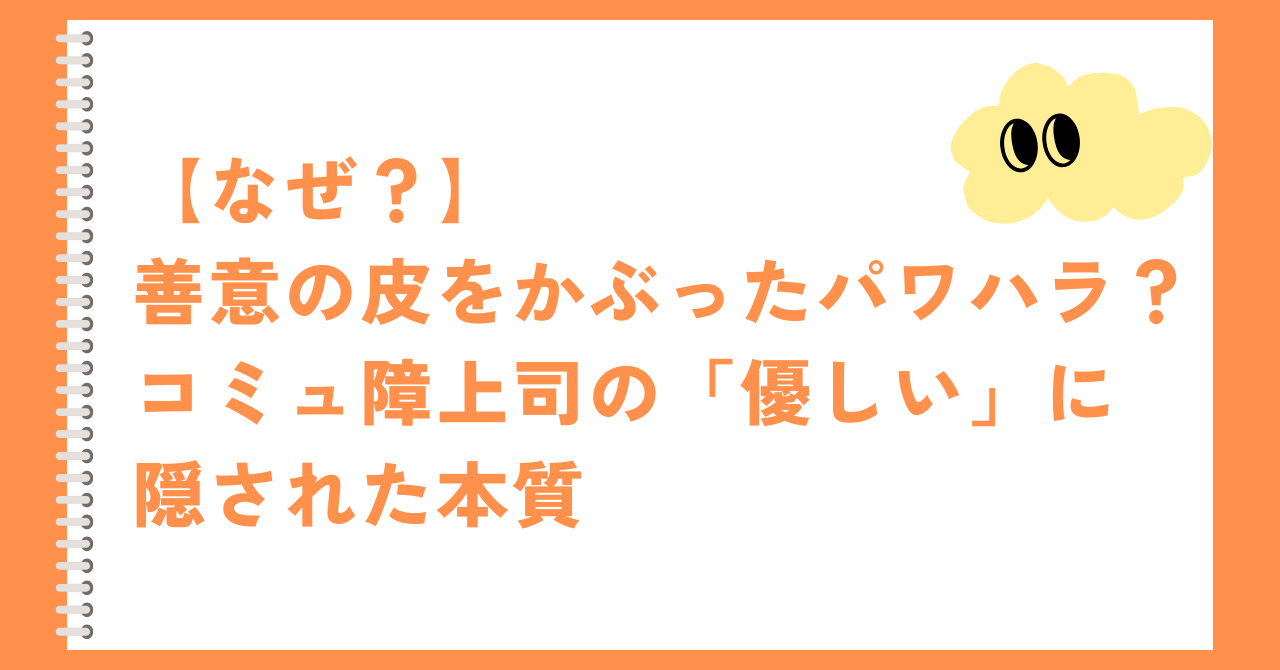
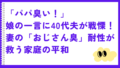
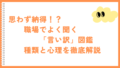
コメント