誰かに仕事を教えるとき、誰かから仕事を教わるとき
「メモとる必要ってあるの?」
という、話題になります。
昨今の人材不足から、わたしが勤務する会社も、たくさんの人を採用してきました。
そして、新人さんが社内教育を受ける様子を観察してきました。
この記事では、
教える側、教わる側から見るメモの必要性や、
メモをとるときの注意などをまとめてみました。
仕事を教える側、教わる側の方の参考になると幸いです。
仕事を教わるときって、メモとったほうがいい?
結論
仕事をちゃんと覚えるなら、どっちでもいいよ!
メモとってもいいし、とらんでもいいし!
そもそも仕事を教える側からすれば、仕事を覚えてもらうことが目的なので、メモは単なる手段。
目的がキッチリ完了するなら、手段はなんでもよいのです。
そもそもなんでメモとる必要があるの?
肝心なのは目的、つまり、仕事を覚えることで、メモは単なる手段にすぎない。
なのに、メモをとる必要があるということは、目的が達成されていないからで、
つまりは、仕事を覚えていないからです。
何回も同じことを聞かれると、
もうっ!いい加減にしてっ!!
覚えれないならメモとってよ!!
こうして職場では、仕事を教わるときにメモ必要?という話題になるのです。
メモをとらなくても仕事を覚える人
仕事を教わる側は、この3つに分類されます。
・メモをとる人
・一部だけメモをとる人
・メモをとらない人
わたしの感覚でみると、メモをとる人は多いですが、メモをとらない人が決して少ないわけでもない。
わたしの夫は、メモをとらない人です。
夫は、たとえ簡単なメモであっても、文章を書くのが苦手なのです。
それでも、仕事はちゃんと覚えます。
同じことを2,3回は聞いてしまうけど、仕事は必ず覚えます。
必ず覚えるので、「メモとったほうがいいよ」などと言われたことはないです。
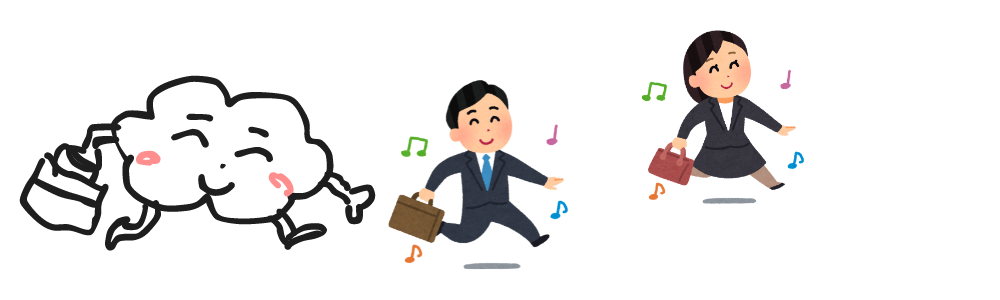
メモは何を使ったほうがいい?
メモは、仕事を覚えるという目的達成のための手段なので、何を使うかは自由です。
一般的に言うメモとは、ノート、メモ帳、手帳などの紙媒体。
サッと取り出して、すぐにメモできるのが長所。
ですが、便利な世の中になったもので、
・スマホ
・ボイスレコーダー
・タブレット
など、音声や動画で記録できるのは、とてもありがたいです。
工場での機械操作や、職人技などを映像で記録しておげば、後で何度も見返すことができるます。
また、他の人とも共有ができるので、自分だけではなく、多くの人にとって有益です。
便利なものは、どんどん活用したいですね。

メモのとり方で気を付けること
気を付けることは、ズバリ…
メモの内容で、どこに何を書いたか分かること。
わたしが観察していた新人さんのなかで、しっかりメモをとっているのに、仕事が上達しないという人がいました。
新人さんのノートには、先輩からの教えがびっしりと書き込まれていました。
びっしりすぎて、新人さんは後から見返すことができなくなってしまいました。
先輩から、こうして、こうしたら、次はどうするんだった?
と聞かれると。
新人さんは、えーっと、えーっと…
ノートをあちこちめくるのですが、結局見つけられませんでした。
仕事で分からない事がでてきた、どうやるのか忘れた、なんて決して珍しいことではありません。
誰でも起こることです。
そのときにメモを見返すことで、仕事への理解が深まるので、メモを見返すことを意識したメモ作りが、ポイントです。
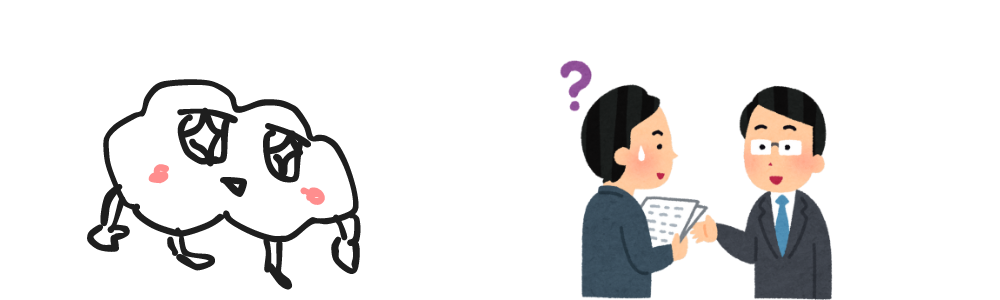
メモのとり方例
新たに仕事を教わるときの、わたしのメモのとり方です。
ノートを2冊用意します。
・書き取り用
・まとめ用
の2種類です。
先輩から仕事を教わるときは、先輩の説明を聞くことに集中し、メモは汚い字でもいいから、ノートの罫線を無視して、
とにかく書き留める。
そして、時間があるときに、そのメモを見ながら、もう一冊のノートにきれいにまとめていきます。
この作業が、面倒に感じると思いますが、まとめることで、理解不足箇所を発見したり、新たに疑問が生まれたりして、より理解が深まっていくのです。
また、まとめノートにインデックスシールを貼ることで、後で見るときに、すぐに目的のページを開くことができます。
後で見返すことができなきゃ、メモをとる意味がないし、
メモを活用できなきゃ、仕事を覚えることができない。
細かいことを言えば、インデックスシールの色を使い分けて、仕事内容別に識別しています。
他には、
ルーズリーフを使って、仕事内容別につづる人。
パソコンや、デスクの仕切りにメモを貼り、仕事を覚えたら外す人。
メモのとり方は人それぞれですね。
メモをとる・とらない以前に大切なこと
今まで、仕事を覚えるのが目的で、メモは単なる手段というお話をしましたが、それ以前に大切なことがあります。
それは、
教える側の負担を意識することです。
教え方が雑な人も確かにいるのですが、今回はちょっと横に置いといて…
わたしの先輩方のお話です。
先輩方は、これまでたくさんの新人さんに仕事を教えてきました。
そして、教わる側の新人さんは様々です。
・理解が早い人
・理解が遅い人
・あせりやすい人
・のんびりな人
先輩は、いろんなタイプの新人さんがいるという事を考慮して、タイプによって教え方を工夫しています。
「時間がかかってもいい、少しずつ成長していこう」
これが、先輩の教育姿勢です。
先輩の部署では、教育期間は約6ヶ月。
はじめの頃はつきっきりで教え、状況をみながら、少しずつ新人さんに任せ、そばで見守る。
困っていれば手を貸し、上達のポイントを惜しみなく新人さんへ教えます。
先輩は、自分の仕事をこなしながら、新人さんを教育しています。
大変だけど、大変な空気など一切ださない。
先輩方の器の大きさに、ただただ尊敬あるのみ。
時間と手間が
めちゃくちゃかかっています。
だからこそ、教わる側の新人さんは、
遅くても、少しずつでもいいから、
仕事について吸収していってほしいです。

メモメモ失敗談
メモは破っちゃダメでしょが
夫の仕事先でのお話です。
新人君は事務所作業の仕事を教わっています。
新人君の仕事は、別部署との連携が必要なので、別部署へ見学に行きました。
先輩が、
「別部署の勉強をちゃんとしてこいよ。しっかりメモするように!!」
と、新人君に声をかけました。
別部署にやってきた新人君は、先輩に言われた通りメモをとっていました。
別部署の先輩がメモをのぞきこみ、
「字きたないなぁ。そのメモ読めるんか?」
と言ったところ、新人君は、
「いいっす。事務所に戻ったら捨てるんで。」
??。唖然とする先輩。
事務所に戻った新人君は、自分で書いた、きたない字のメモをビリビリと破いて、ゴミ箱へポイッ。
しばらくして、新人君は会社を辞めました。
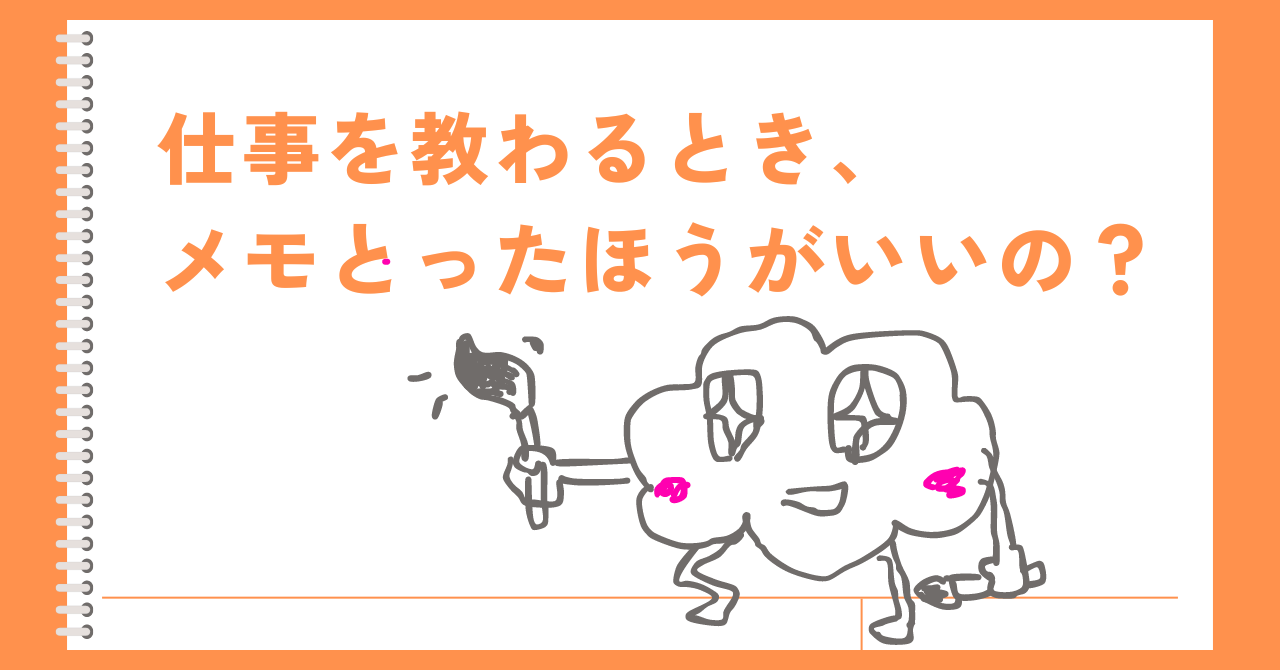

コメント